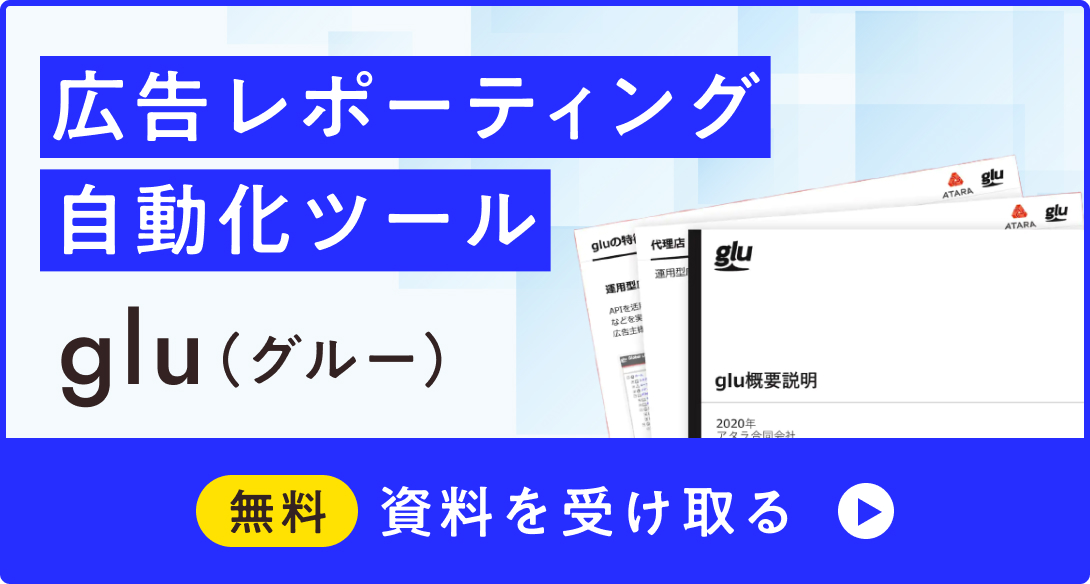目次
『プログラマティック広告最前線』連載の趣旨
デジタル広告が総広告費に占める割合はグローバルでみても年々増加しており、このデジタル広告のデファクトスタンダードとなっているのが、広告在庫の自動売買に対応するプログラマティック広告です。5Gに代表される通信システムの発達やIoTの普及も相まって、テレビや屋外/交通広告(以下OOH)といったデジタル広告に分類されない媒体においても、プログラマティック化が進んでいます。
そこで本連載では、マーケティング先進国の欧米の事例を中心にプログラマティック広告の最前線をお伝えするとともに、最前線の少し先の世界を考察しています。また、日本国内の最新事例についても、キーパーソンとの対談を通して紹介していきます。
第二回では、株式会社LIVE BOARD 代表取締役社長の神内一郎さんに、日本国内のプログラマティックOOHの最新事情についてお聞きしました。
リンク:
今回の話し手:日本経済新聞社の大塚栄一さんと國友康弘さん
第三回となる今回は、広告在庫を提供するパブリッシャーに焦点を当て、日本のパブリッシャーの最前線を対談を通して紹介します。
プログラマティック広告がデジタル広告のデファクトスタンダードとなり、GoogleやFacebook、Amazonなど巨大プラットフォーマーに広告費が集中する中で、パブリッシャーは変革を迫られています。マーケティング先進国の欧米ではパブリッシャーのプラットフォーム化構想まで話が発展している状況です。
参考:
また、昨今の欧米におけるGDPRやCCPAといった個人情報保護に関する法整備の影響により、3rd Partyデータの取得が難しくなることが予測されると同時に、2nd Partyデータ、すなわちパブリッシャーの1st Partyデータの重要性が注目されています。
そこで、本対談では、「Beyondインベントリー」をスローガンに日経IDという1st Partyデータの積極活用を掲げた日本経済新聞社(定期誌『MarkeZine』第37号を参照)の大塚栄一さん、國友康弘さんに、パブリッシャーとしてのプログラマティック広告に対する最新の取り組みとデータ活用を起点とした今後の事業構想をお聞きしました!
リンク:
話し手:
日本経済新聞社
デジタル事業 メディアビジネスユニット ユニット長 大塚栄一様
デジタル事業 メディアビジネスユニット ユニット長補佐 國友康弘様
聞き手:
アタラ合同会社 高瀬優
※このインタビューは2019年4月に実施されました。
プログラマティック広告が占める割合は1%に満たない
高瀬:プロフィールと業務内容を教えてください。
大塚:1988年に入社し、新聞広告の営業でキャリアをスタートしました。日経本紙をはじめ日経産業新聞、日経ネットや日経電子版など様々なメディアの広告営業を続けてまいりました。2015年に日経電子版の営業部門に異動となり、5年目となる今年の4月から、メディアビジネスユニットのユニット長に就任いたしました。
メディアビジネスユニットとは、日経電子版をプラットフォームとするビジネス部門で、主たるポートフォリオはネット広告と日経IDを活用したビジネスの二つとなります。
営業チーム、営業支援チーム、マーケティングチーム、N-Brand Studio、業務推進チームで編成されます。N-Brand Studioとはブランデッドコンテンツの制作や日経電子版のライフスタイルサイト、NIKKEI STYLEの編集機能の一部を担っています。元編集記者経験者も多く、制作するコンテンツの質に定評があります。
國友:私も新聞広告営業の出身で1992年入社です。海外での勤務を経て、2010年に日経電子版の創刊の準備期間にデジタルの方にコンバートし、それから9年この部署で基本的には同じことをやっています。
最初の6か月間の営業で、ネット専業の広告会社様との向き合いの中で、新聞広告営業としての向き合い方、やり方がだいぶ違うなと痛感し、「もう少しロジ(兵站)がないと戦えません」と当時のGMに上申したところ、そのあと2か月後ぐらいに「じゃあ君が」ということでバックオフィスに入り、プロダクトマーケや在庫の管理などをやるようになりました。
この3月までデータ活用を中心とするプロダクトマーケと配信からレポートまでのオペレーションを統括する立場におりまして、この4月からはCRM/SFA活用推進、商談創出による営業支援に携わっています。

高瀬:御社の広告収入の中で、プログラマティック広告が占める割合は大体どのぐらいでしょうか?
國友:1%もないです。我々としてはプログラマティック広告だから価格が安いことはないと考えており、広告配信を効率化したい目的をお持ちのお客様に対してはPMPで対応しております。
日本の広告主様のほとんどは、プログラマティック広告はパブリッシャーが余剰在庫を提供してくれるマーケットだから安く買えるはずという期待値をお持ちです。一方で、これは我々の考えとは異なるため、そういった意味でいえば、私たちのような場を必要とするお客様で、かつ広告配信とかレポーティングといった業務を効率化されたいというお客様が1%もいないということだと理解しています。
高瀬:そうしますと、残りの99%というのはいわゆる純広告といいますか、在庫保証型のプロダクトになるわけですね。
國友:おっしゃる通りです。ただ期間と配信数の両方を保証する予約型広告のみが純広告かというと違うような気がしていて、希少なセグメントに広告配信をされたいというご要望をいただくことがあります。それを精緻に予測して期間と配信数を保証するのは、非常に難しいです。我々は結構ギリギリまでやっていますが、それでもできない場合があるので、期間か配信数のいずれかを保証する運用もしています。こうした販売方法とPMPは相性がいいですね。
高瀬:グローバルにみてデジタル広告の中でもプログラマティック広告がスタンダードになりつつあるという流れの中で、広告収入に占める割合が1%というのは意外だなぁと思いました。
國友:昨今のアドフラウド、アドベリフィケーションの問題もあり、我々のような信頼のおける媒体に直接お声がけをいただくことが改めて増えている背景もあって、プログラマティック広告ではなく純広告の比率が維持されているのではないかとも考えています。運用の効率化だけでなく、一定の質を担保したインベントリを安価なCPMで購入したいという方々が多いということの裏返しだと理解しています。
高瀬:プログラマティック広告=安価なCPMというイメージが定着してしまっていることの裏返しでもあるということですね。
國友:はい。そういったこともあってか、今のところPMPは外資系企業が中心ですね。前提として、PMPだからといって純広告より値段が下がるとは思っていないわけです。どこに基準を置くかにもよりますが、日本のネット広告の料金相場は欧米に比較するとだいぶ安いですしね。
高瀬:先ほどプログラマティック広告が広告収入全体に占める割合が1%未満と仰っていましたが、この割合は変化してきているのでしょうか?
大塚:いろいろと検証した結果、現在では減っていると言えるでしょう。日経電子版の月間アクセス数は約4.7億です。デバイス毎の内訳では、PCとスマートフォンでほぼ半々です。この在庫規模なので例年繁忙期の3月にはほぼ完売となります。今年の3月には初めて繁忙期料金を適用させていただきました。心苦しかったのですが、ご理解をいただき受け入れていただき、需要は変わりませんでした。よってプログラマティック広告に取り組む余地がないというのが現状です。

昨年まで我々の組織は広告・IDユニットという名称でしたが、本年からメディアビジネスユニットに変更しました。広告媒体としての日経電子版ではなく、日経電子版をプラットフォームとした企業様とユーザー様をつなぐ機能、サービスの提供をビジネスとする組織とミッションを再定義した結果です。
弊社とお付き合いの深い企業様はIT・通信、高級自動車ブランド、金融機関、自治体、ラグジュアリーブランド等になります。一般的な広告市場における企業群とは大きく異なることをご理解いただけるかと思います。よって一般的なネット広告の提案にとどまらず、コンテンツマーケティングの支援、データの利活用、イベントの運営のお手伝いなど通じて、広告主というよりビジネスパートナーとして関係を構築させていただいています。
高瀬:PCからのアクセスも一定数あるんですね。
大塚:オフィスでのデバイスはまだまだPCが多く、アクセスが許されているメディアは限定されています。その環境が日経電子版のアドバンテージの一つととらえています。
高瀬:年々モバイルの比率は上がってきていますか?
大塚:上がってきています。今年はついに半分を超えました。しかし爆発的に増えてきたというわけではありません。
國友:朝の通勤時にモバイルでお読みいただくところと、お昼のタイミングにPCでお読みいただくところの二つの山があります。朝、職場に着かれてから仕事に入る前に気になる記事をチェック、昼もオフィスのPCでお読みいただいているようです。そういう意味でモバイルシフトはある程度落ち着いたという感じはあります。
広告在庫に依存しないビジネスをデータで実現
高瀬:「Beyondインベントリー」に関して、どういうことを目指されているのかというところと、それを掲げた背景をお伺いさせてください。
大塚:我々が広告ビジネスで重視しているのは「ユーザー体験を損ねない」「広告主のブランド価値を損ねない」という二つのポイントです。そしてこの取り組みを続けていくと広告的な在庫の伸びで成長を目指すことが難しくなります。
よって限定された在庫の中で広告ビジネスの最大化を目指すのと同時に、日経電子版と日経IDユーザーのリソースの上に新しい収益基盤の開発を目指す戦略が重要になってきているということです。それが「Beyondインベントリー」が持つ意味です。
新しい収益基盤開発の方向性は日経電子版ユーザーの「おはようからおやすみまで」「入社から退職まで」の中でのビジネスです。現在運営しているのはタクシー内のデジタルサイネージに日経電子版の記事と広告を配信するもの、シェアオフィス、ビジネスマンに向けたイベント情報サイト、転職情報サービスだったりします。こうした取り組みを進めることでポートフォリオを徐々に変えていこうと考えています。
参考:
加えて「読む日経から使う日経」という考え方も事業開発の一つの方向性です。新聞を情報発信メディアとしてだけでなく、日経電子版ユーザーのビジネスのアクセラレーターツールとして使っていただけるような可能性も模索しています。
高瀬:広告事業に限らず日経IDのデータをフル活用した新規事業をこれから創始されていくというイメージですね。
大塚:そうお考え下さい。
高瀬:広告の視点でお伺いすると、今年の2月にVerizon Mediaの動画DSPと日経IDのオーディエンスデータとの連携を開始されていましたが、これもBeyondインベントリーのお取組みの一環でしょうか。
参考:
國友:そうですね。そもそもでいうと日経電子版のユーザーって日経ではあまり動画をご覧にならないです。日経電子版は楽しむメディアではなくて、仕事の筋肉に必要なプロテインのようなものなので、その中で動画をじっと見るということはなくて、もし業務中に動画を見られることがあればそれは日経電子版ではなくてWebセミナーかもしれないと想像しています。
そうは言っても動画広告自体は成長しているマーケットです。日経電子版をご覧になっている方々が他のメディアで動画をご覧になっているとき、特にインストリーム枠に広告を配信できればと考えてやっています。
DSPとのデータ連携はディスプレイ広告で始めました。日経ユーザーにリーチしたいというお客様にまず使っていただいて、そこでの効果が良ければ日経電子版にステップアップしていただけるようにというドアノック的な位置づけの商品としてご提供しています。
高瀬:実際そういった事例も結構あるのでしょうか?
大塚:日経IDのオーディエンスデータを活用したDSPでリードを獲得している広告主が、日経IDの魅力に気づき日経電子版での広告配信を実施、手ごたえを得て継続受注。の例はあります。ただし本来的にはリードの育成を目的としたブランディング施策との連携が理想で、それこそが満足度の高い継続的なお取引につながると考えています。
高瀬:仰るように、ブランディングが主になってくると思うのでそこにいきつくまでっていうのは事業のタイミングもありますし、ステップを踏んでというかたちになりますよね。いまどのぐらいのDSPと連携をされてデータ提供されていらっしゃるんですか?
國友:MarketOne®とOath Ad Platform、それにPeople Driven DMPです。
GDPR以降潮目が変わった
高瀬:こういったDSPへのデータ連携は今後拡大していく予定はあるのでしょうか?
國友:複数のDSP事業者様からお声がけをいただきますが、配信面が重複しているなら、現状で事足りるという認識です。
もう1つは昨今のユーザーの個人情報保護とそのデータ活用に関する規制があります。弊社は日経IDやcookieの情報は「こういうことに使われます」とお客様にお伝えしているわけですが、すべての用途を承知しているかというと、そうは思えないです。大塚ともよくディスカッションするんですが、用途を絞り、もっと丁寧に説明した方が良いという認識です。

仮にそれによってオプトアウトされるお客様がいても、そのお客様に日経電子版上でコミュニケーションをとれるという事実には変わりがありません。
今までのように、取得コストの安さに依存するといいますか、ユーザーがよく知らないうちに取っていたデータでビジネスをするという時代ではないのかなと思います。
日本の場合、アメリカ型ではなくEU型という方針は見えてきているので特にそう感じています。実際フィナンシャル・タイムズもGDPRの施行後にオープンオークションはやっていないですし、接続先のDSP自体をものすごく限定するなどプログラマティックそのものにも限りなく消極的な印象です。
我々のようなそれほど巨大なインベントリを持っているわけではないけれども、読者の顔が見えているビジネスプレミアムメディアにとっての大きな方向性はそっちなのだろうなと理解しています。
高瀬:なるほど。ひとつの大きな流れとして、GDPRをきっかけに直接ユーザーと関係を持ちかつ会員データを保有するパブリッシャーに注目が集まっています。これまで広告主がDSPで広告配信する際に活用していたパブリックDMPなどの3rd Partyデータが減少していくという予測が背景にあるのですが、御社のデータ、これは広告主からみると2nd Partyデータになりますが、先ほどのお話だとこれを積極的に提供していくという動きは難しそうですね。
大塚:積極的には考えづらいと思います。
國友:仮にその方向に動くのであれば、お客様が明示的に同意してくださっているという前提を整えた上で進めるのが望ましいと考えます。
以前の想定とはまた違った世界というか、それこそパブリッシャートレーディングデスクをがっちり運用して、日経電子版のインベントリの価値を守りながら日経IDのデータとDSPの連携を進めてといった構想はありましたが、GDPR以降潮目が変わっているという認識ですね。
高瀬:当初はそういう構想はあるにはあったということですね。
國友:ありました。2017年ぐらいはそういうことを結構真剣に議論してビジネスプランを書いていました。
高瀬:同様にGDPRの観点でいうと、3rd Partyデータの減少が予測される中で、コンテキストに原点回帰するといったトレンドもあります。御社の記事もコンテキストに応じてある程度分類可能かと思いますが、記事のコンテキストを活用した広告商品を提供するといった構想はあったりするんでしょうか。
大塚:そういう方向かなと我々も検討を始めています。またこれは広告に限った話ではなく、電子版ではパーソナライズもテーマの一つなのでそこにも紐づいてきます。そもそも個人情報は利用のハードルだけでなく、取得することのリスクも高まっていくと考えているので。
高瀬:個人的には、コンテキストからオーディエンスを割り出す方が、広告のパフォーマンスはもちろんユーザービリティの観点でも優れているのではないかと考えています。例えば、各コンテンツをどういったユーザーが閲覧しているか分析できれば、これをベースにオーディエンスを定義することで適切なユーザーにリーチすることが可能ではないかと。
國友:特定のキーワード、テーマの日本経済新聞の記事群をお読みいただいている読者が一気に増えた企業があったら、それはそのテーマについての関心がその会社の中で高まっているということなので、そういうモーメントを捉えていくことも、やっていければ良いなと思っています。
適切なコンテンツを適切なタイミングで
高瀬:もう一つの大きな潮流として、パブリッシャープラットフォーム構想があるかと思います。この背景として、GoogleやFacebookなど巨大プラットフォーマーに広告費が集中する中で、それ以外の選択肢としてパブリッシャーが広告主から選ばれるようなプラットフォームを目指すということがあります。先ほどのお話でいうと、御社としてはスケールという観点でプラットフォーム、パブリッシャートレーディングデスクというのも難しいという見解でしょうか。
國友:そうですね。あまりいまは真剣に収益増加策の一つとして検討している感じではないですね。それよりはいかに適切な広告コンテンツを適切なタイミングでお客様に届けるかという方が優先順位としては高いですし、我々側でも適切なコンテンツを広告主様のためにつくる、お読みいただいている状況をお伝えするということを通じて、商品ですとか企業とのエンゲージメントを高めていくお手伝いをさせていただくことの方が、優先順位は高いと考えています。
高瀬:パブリッシャーの規模も様々だと思いますが、パブリッシャー自身がプラットフォームになるというような動きは俯瞰的にみてどのように見えていますか?
大塚:日経電子版はユーザーも広告主も極めてユニークなので、他のメディアと連携しプラットフォームとなる必然性がなかなか見いだせないでいます。
日経電子版ユーザー、多くはビジネスマンですが「おはようからおやすみまで」をコミュニケーションの機会ととらえると連携先はメディアではなく、タクシーの車内広告なのかもしれないし、社員食堂のディスプレイかもしれないし、電車の中のディスプレイなのかもしれないし、駅のデジタルOOHなのかもしれません。
高瀬:先ほどGoogleやFacebookといった大手プラットフォーマーへの広告費集中に少し触れましたが、御社からみてこういったプラットフォーマーはどのように見えていらっしゃるんでしょうか。
國友:テクノロジーとそれを生かした商品・ソリューションの打ち出し方についてはいつも学びが大きく、尊敬の念を抱いています。ビジネス面でいうと、DSP最大手のGoogleと取引しないという選択肢はないですから、技術的な側面でいうとマッチレートをちゃんと高めていくような施策は必要だと考えます。ただ、冒頭お話ししたとおり、プログラマティックが広告売上全体の1%未満なので、そこまで優先順位が高い話ではありません。
大塚:ご承知の通り彼らはメディアとの関係性をとても重視しています。弊社も様々な連携や提案をいただいています。少し前にはVRコンテンツを広げようと共同プロジェクトにトライしたこともあります。また社内のほかの部門ともいろいろと接点はあるようです。彼らの動きは極めて先進性に富み、刺激的なので、今後ともいろいろと接点は持っていこうと考えてはいます。
Facebookとは親和性は高いかなと思いますが、ごくごく普通のパブリッシャーがやっていることしかまだできていないです。
高瀬:ありがとうございます。最後に、御社がパブリッシャーとして今後力を入れていきたいことや構想などございましたらお伺いできますでしょうか?
大塚:新聞社の最大の強みがコンテンツ力であることに変わりはありません。丁寧な取材で積み上げたファクトから紡ぎだすニュースや解説が我々の競争力の源泉です。ここはデジタルで代替できるものではありませんが、デジタルやデータの活用により一層質の高い記事となる可能性があります。またデジタルならではの表現力や配信方法がこれまで以上に記事を魅力的に見せることでしょう。
そもそも新聞ビジネスは整備された製造・流通システムと読者の習慣の上で成り立っていました。それがテクノジーの進化により大きく変わってしまった。そしてこれまでの延長線上には成長も持続もないということに気づかされたわけです。この変化への対応がメディアというより企業としての勝負の分かれ目になると感じています。
デジタル時代のジャーナリズムの在り方、新聞ビジネスのありかたを全社で模索し続けるということが、構想となるのでしょうか。
國友:デジタル事業の他部署が提供する「日経テレコン」や「日経バリューサーチ」、「日経スマートクリップ」といったデータベースサービスと我々の提供するサービスの垣根が溶けてきているのを感じています。
事業会社の潜在的な顧客の選定・発見から受注に至るまでの過程を見ていくときにコンテンツの重要性を改めて感じています。我々が生み出している、あるいは調達しているコンテンツとユーザーデータを組み合わせたサービスというのは今後もっとやれるだろうと思いますし、ご期待の声も結構いただくので、そこには対応していきたいですね。
大塚:最近我々が意識し始めているのは次のデバイスについてです。デバイスの最終形態がスマートフォンとは思えないからです。3年後、5年後に新たなデバイスが普及すれば、広告やビジネスはもちろんのこと、ジャーナリズムやパブリッシャーの在り方も変わります。
我々のビジネスの基盤が大きく変わってしまったように、現在の基盤も最終形ではないと考えています。