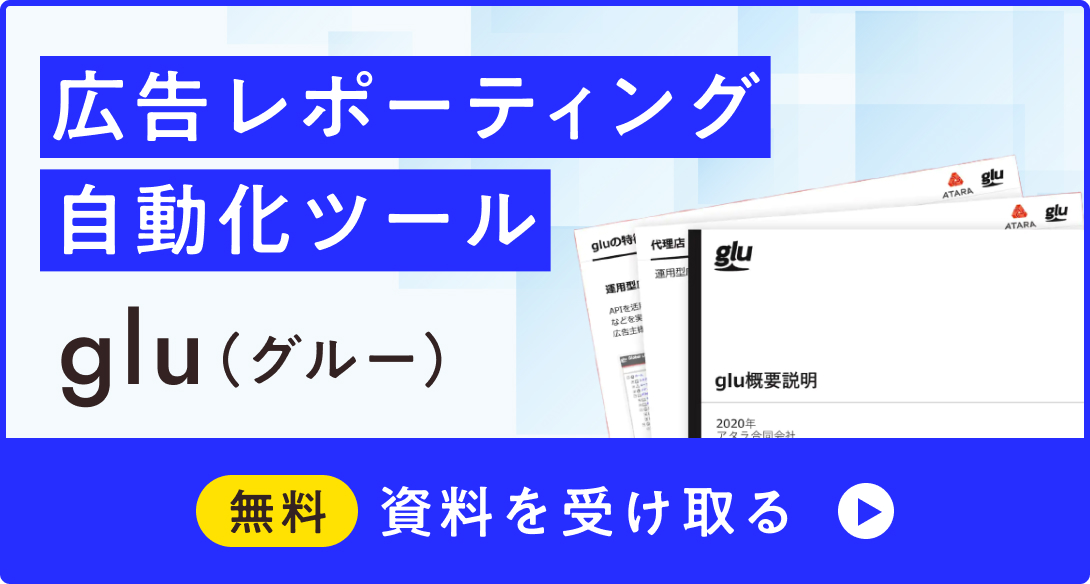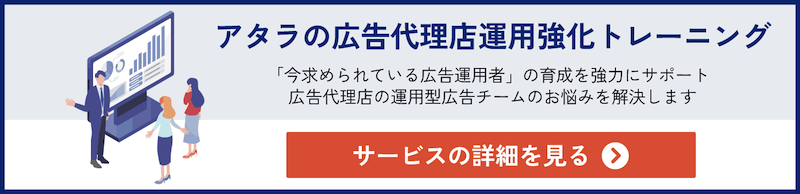
話し手:山本直人さん
聞き手:アタラ合同会社 杉原 剛
編集:アタラ合同会社 井谷麻矢可
※このインタビューは2018年8月22日に実施されました。
目次
限界を迎えた日本の人材育成システム
杉原:まずは自己紹介をお願いします。
山本:現在フリーランスのコンサルタントをしている、山本です。主に一般企業のマーケティング人材を育成するキャリアコンサルティングと、ブランド開発などの純粋なコンサルティングの2つのコンサルティング業務を行っています。業務の7~8割はこういった現場の仕事が多いのですが、他に執筆業や青山学院大学で約10年間メディアとマーケティングの講義をしています。
杉原:フリーランスに転身される前は何をされていたのですか?
山本:フリーランスになって14年経ちますが、それまでは博報堂に18年在籍していました。入社した当初はクリエイティブ部門でコピーライターを務め、30歳からは研究開発に転じて消費者調査やブランディングを経験、ブランドコンサルティングの組織を国内で初めて立ち上げた際のメンバーにもなりました。
その後は人事部門で人材開発やキャリア開発に携わりました。もとは専門スキルの開発が主でしたが、途中から新入社員の研修にも関わり、そこで得たノウハウを活かして何かできるのではないかと思い40歳からフリーランスに転身しました。杉原さんとの出会いは、とある方の紹介で新入社員教育を私に任せていただいたことがきっかけでした。
杉原:もともとキャリア形成やスキル開発に興味があったのでしょうか?
山本:研究開発で様々な研究をしても、それを使う人が理解していないと結局はどうしようもないと気づいてからです。
杉原:博報堂さんのような大手企業だと、研修制度も整っている印象があるのですが。
山本:博報堂は他企業と比べてもしっかりと研修制度が整っていました。しかし新人研修などで基礎は叩き込まれますが、その後勉強するかしないかで個人の差が大きく分かれていました。もちろん新人研修以外の研修制度も充実してはいますが強制的なものばかりでもないので、そこで危機感を持って学ぶ人と学ばない人の差が出ます。
危機感を維持するには社員を取り巻く環境が重要で、小さな企業でも皆が学んでいれば危機感は維持できます。むしろ大企業のほうが部門や部署で環境がまちまちなので、差がつきやすいのではないでしょうか。

杉原:キャリア開発やスキル形成において、昨今ニーズの変化は感じられますか?
山本:事業会社から内部の人材育成を依頼されるケースが増えました。これまでエージェンシーに発注する側だった人たちが「自分たちでも根っこの部分について考える必要がある」と危機感を持ち始めたイメージです。
杉原:ここ3~4年で、ライト/ヘヴィーに関わらず広告主がインハウス化を進める流れがあると感じています。こうしたトレンドも加味しているのでしょうか?
山本:もともと潜在的にあった危機感が、どんどん顕在化しているのだと思います。これまで日本の大企業は、職種別採用をしてきませんでした。要はマーケティングのプロを育成せずにエージェンシーに相当のアウトソーシングをしてきた。
この方法がそろそろ限界を迎えていると気づき、事業会社も危機感を持ち始めたのだと思います。限界だと気づいた理由は2つ。1つ目は様々な外資系企業のやり方を目の当たりにしたこと。2つ目はデジタル化が進んだ結果、既存のエージェンシーでは対応しきれない部分が出てきたことです。
杉原:ソーシャルの登場により企業と消費者が直接コミュニケーションをしなければいけない状況になったことも大きいのではないでしょうか。また、データドリブンの重要性が認識されてきており、これまでのデータ丸投げ体制をやめてデータをきちんと読み取り、どう使いこなせばいいのかを事業会社自身が考えなければいけない状況になってきていると思います。
山本:技術の変容と人材の変化がクロスし、新しいスキル形成・キャリア開発の在り方が求められる状況が生まれているのでしょう。日本の人材育成システムが限界に達しているところに新しい技術が入ってきて、今までのように総合職・技術職を採用することが意味を成さなくなってきている。そのあたりの人事構想を依頼されるケースも増えています。
杉原:旧来の人事異動制度では専門性が身につかないですね。
山本:現在、旧来の方法を変えようと模索する企業は増えてきています。例えば旧来の人事ピラミッドでは対応できないため、ピラミッドから枝分かれさせて報酬を柔軟にするなど。早期から制度改革に取り組んだ企業にはいい人材が集まり、出遅れた企業にはいつまでたってもいい人材が集まらない。そこで企業間の人材レベルの差も生まれているように感じます。
万能感を持つことの危険性
杉原:デジタル技術が進化する中で、デジタルマーケティング分野に携わる人たちの能力やスキルについてはどう思われますか?
山本:デジタル分野に携わる若手は技術に対する適応力が高く、学べばすぐに吸収できる人が多いと思います。ただそれゆえに「万能感」を持ちやすいという危うさがあります。ロールプレイングゲームで例えるなら、まだボスキャラを知らない初期の勇者のようなものです。危機感を持たずに万能感を維持したまま仕事が続けられるかと言うと、恐ろしいことにデジタル分野においては「それなりには」できてしまうのです。
インターネット広告業界は未だに規模が縮小したことがなく、何かしら仕事がある状態です。また、近年ウェブ広告の分野は進化が著しく、テクノロジー自体がものすごく洗練されてきています。つまりある程度勉強すれば誰にでもでき、かつ失敗しにくくなっているのも、万能感を煽る要因の一つだと思います。
しかしこれから必ず広告が縮小する時は来る。そういった環境の変化が生じた時こそ足腰の強さがすごく重要になると同時に、そこで差がつくと思います。マーケティングの本質である「人間はなぜそのモノを選ぶのか」という根本的な理屈や感覚、つまりファンダメンタルな部分を養っていないと、ITの技術だけで感じていた万能感はまったく通用しなくなります。
足腰の強い運用者になるには
1.「地理」に詳しくなる
杉原:例えばダイレクトマーケティング系のクライアントであれば話せても、ブランド系のマーケターのニーズを引き出せないデジタルマーケティング従事者って意外と多いのではないかと感じています。そうした現状に危機感を抱き、ファンダメンタルな部分について学ぶ気はあるが、どこから勉強し始めていいのかわからないという若手は多いと思います。まずはどのような点を押さえるべきでしょうか?
山本:マーケティングの基本としてまず重要なのは、人口や年齢層、居住地や所得、産業構造など、義務教育で学ぶ「地理」の知識を整理することです。日本の人口を聞かれて答えられる人は多いですが、世帯数や出生数となるとぱっとわからない人が多い。しかし例えば洗濯機を販売したければ、世帯数を知る必要があります。そうした知識を整理し、スケール感が直感的にわかるようにしておくと、クライアントと話す際に話がしやすくなったりもします。
例えば、世間で騒がれている「ビール離れ」。現象として「嗜好の多様化」「苦いものは飲まない」「ハイボールが流行っている」などが挙げられますが、その本質的な理由はなんでしょう?それは、日本を含めた先進国では第二次産業従事者が減っていることだと思います。
低アルコールで炭酸の効いたビールは第二次産業のように現場で汗をかき、肉体労働をした後に飲んでこそ美味しいと感じる飲料です。一方、第三次産業に従事する人たちは、夜中までパソコンとにらめっこした後に、果たして大ジョッキで苦みの効いたビールをがぶがぶ飲みたいと思うでしょうか。それよりも缶チューハイやハイボールのように爽やかな飲み口のものを求めるのではないでしょうか。ところ変わって中国のように第二次産業が伸びてきた国では、ビールの売り上げも伸びてきましたが、近年は減少に転じています。そういう総合的な知識を意識してニュースなどを見ていくと、仕事に繋がるヒントはたくさん転がっています。
杉原:携帯電話会社も例になりそうです。もちろん競合キャリアも気にしていると思いますが、生活者の可処分所得、可処分時間の中でどれくらい携帯電話が占めているかも見ていると思います。本や飲食にどれだけの時間とお金を費やすのかを知れば、比例して携帯電話、キャリアのコンテンツに割ける時間やお金も分かってくる。そういう別角度からの視点を持つことはとても重要だと思います。

山本:他にも、音声入力はアメリカから発達した技術で、クルマ移動との相性が良い。一方で日本ではフリック入力と日本語の相性が良く、都市部は公共交通機関での移動が多い。つまり、日本においては音声との相性は良くないかもしれない。交通機関×ITの議論はあまり耳にしませんが、そういった視点で見てみるのも面白いですね。
杉原:アメリカで流行っているからといって必ずしも日本で流行るとは限らないし、流行るかもしれないが使い方は全然違うかもしれない。日常の何気ない事もまずは疑ってみることが大切ですね。
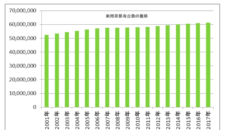
「若者の車離れ」などと言われることが多いが、実は乗用車の保有台数は減っていない。
2.人の心を「深く」とらえる(あるいは人の心を「疑う」)
山本:2つ目は、人の心を「深く」とらえることです。ブランドの担当者は、自社商品が売れた直後から「本当に売れたのか」を検証します。安くして売れるのは危険なことだし、キャンペーンを打って売れるのは当たり前。本当にそのブランドが好きで買ってくれているのか疑問を持つことはとても重要です。つまり、消費者の行動だけでなくその行動の根底にあるブラックボックスの部分を見極めなければいけません。
それが、人の心をとらえることに繋がります。しかし昨今、見極めるプロセスの重要性が軽くなってきていて、特にデジタルマーケティングに携わる人はその感覚が薄い人が多い。そうするとブランドの担当者とは話がしにくくなります。この商品を本当に買うのか?買った後どうするのか?なぜ買うのか?を常に疑ってみるクセをつける必要があります。

行動そのものに着目するのではなく、その裏にある「行動の理由」に目を向けることが重要。
杉原:癖づける方法は何かありますか?
山本:自社の競合以外にも新しい商品が市場に出回るたびに、これは本当に売れるのか、売れないのかを考えてみることです。さらに一人で考えるというよりは、皆で考えられる環境を作るほうがベターです。例えば週に1度チームメンバーで集まって、自分が売れると思う商品を持ち寄り、予想ゲームをするなどでいいと思います。これならばコストも時間もかからずに、疑い癖をつける風土を作ることができます。
杉原:私も集合知は重要だと感じています。アタラでも毎週勉強会を開催しており、事案の情報共有や、プロダクトのアイデア出しをしています。そんな時、自分では思いもかけなかった意見が聞けたりします。そこまで大げさにしなくても、少し周りに聞いてみるだけでも全然違うというのは肌感覚としてあります。
山本:デジタルマーケターも事業主のマーケターと同じような会話をしてみるということが大切です。
3.課題解決の前に課題発見をしよう
山本:3つ目は、オリエンテーション(課題発表)を待っていてはいけないということです。例えばプレゼンテーションでは、オリエンテーションを待っている時点で他社とスタートが一緒になります。そうなった際に一番怖いのは最終的に価格で勝負せざるを得なくなること。そうならないために自分でオリエンテーションを書いてみるのです。
つまり、課題発表を待って解決策を提案するのではなく、先にクライアントが抱える課題を発見してしまうのです。そこまで踏み込んでしまえば、きっと競合に勝てます。プロの経営コンサルタントなどもこうした技術を持っています。それを可能にするためには、クライアントとの日常会話や世間話からロジックを読み解き、今相手が何に困っているのか、クライアント企業が何を目指しているのか、ベンチマークしている企業はどこなのかなど、クライアントの持つ課題感を発見する必要があります。
興味深いことに、例えばアルコール飲料メーカーが自動車メーカーをベンチマークとしているなど、全く別業種の企業をベンチマークしている場合もよく見られます。業種は違えど、会社全体のマネジメント体制や社員の長所発掘方法などに共通点があるからです。優れたマーケターほどそうした独自の指標を持っています。そういったところまで踏み込んで聞き出せると、マーケターの嗜好性や目指すものがわかります。加えて、どのようなメディアに接しているかによっても、マーケターの見ている方向がなんとなくわかります。
4.ニーズ+モチベーション
山本:4つ目がニーズ+モチベーションという発想です。ただニーズに応えるだけでなく人の心を動かす、「動機づけ」を大切にしたいと思います。そして、ニーズを汲むだけでなくモチベーションを上げることまでできる人材になってほしいと思っています。
例えばインターネットで「夏休み」と検索したら、旅行関連のサイトがたくさんヒットします。確かに旅行の情報を提供することでユーザーのニーズは満たせるでしょう。しかし中には、夏休みに旅行をしたくない、一人で過ごしたいと思っている人も潜在的には多くいるかもしれない。その際に旅行以外の過ごし方を提案し、背中を押してあげることでモチベーションを高められるかもしれない。モチベーションはマーケティングの中でも意外と研究が進んでいない分野の一つですが、一方でニーズに関してはデジタル技術の進歩により細かくわかるようになってきました。AIの技術の進歩によりいずれはモチベーションも見えるようになるかもしれませんが、もう少し先の話ではないかと思っています。
例えば、バーテンダーはAIの進化でなくなる職種の一つと言われていますが、私はまだまだなくならないと思います。ニーズを言われてそれに合うカクテルを作ることはAIにもできますが、本当に優秀なバーテンダーはお客様の顔色や体調、連れは誰かなどを観察して、その都度レシピを変えます。潜在心理を洞察し、モチベーションに働きかける技術が確立するまでの間は、人間が「人はどうすれば心を動かすのか」の洞察を深める必要があります。
杉原:ニーズの話でいうと、検索連動型広告が最たるもので、流入ワードを見ていても「こんなにニーズがあるのか」と驚くことがよくあります。ニーズの多様性が見えるようになったからこそ、マイノリティとされてきた人たちにも居心地の良い生き方ができるようになった側面もあると思います。その一方で、サービスや商品の提供者側は一定の量を販売しなければいけないため、マイノリティにまで手を付けられないでいると感じることもあります。
山本:遠心力と求心力ですね。世界が一つになる動きと、細分化する動きが同時並行で起こっている中で、今はまた量を追う動きが出てきています。10年以上前は、小規模で資金のない企業でもインターネットなら売れる、世界から見つけてもらえる、つまりマイノリティの味方というイメージがありましたが、今は違ってきている。大きなニーズに対応しようとするから、ニーズの裏にある潜在的なモチベーションについて考える隙も無いのかもしれません。
杉原:細分化と集約化を繰り返す中で今は集約化に寄っているかもしれませんが、これからまた変わるかもしれない。どんなに外部環境が変わろうとも対応できる人材になるには、技術的な面だけでなく今日教えていただいたようなファンダメンタルな部分の力を養うことが重要ですね。
山本:本日お話した内容は、私の著書『マーケティング演習ノート』にも詳しく記しています。興味のある方は手に取ってみていただければ幸いです。

【山本さんの新著】
『50歳の衝撃 はたらく僕らの生き方が問われるとき』

著者:山本直人/出版社:日経BP社/発売日:2018年8月8日/価格:単行本 1,404円、Kindle版 1,300円
人生100年と言われる時代において、50歳は言わば折り返し地点。同書では、著者が様々なビジネスシーンにおいて見聞した事実をもとに25の葛藤物語を描いている。物語はいずれも50歳前後のミドル世代が直面しやすい人生を左右する経験ばかり。人生の折り返し地点で葛藤する人に「生きるヒント」を与えてくれる、ミドル世代必読の書。